WEB本の雑誌>【本のはなし】作家の読書道>第20回:片山 恭一さん
第20回:片山 恭一さん (かたやま・きょういち)

恋人を失った少年が2人の日々を振り返る切ない物語『世界の中心で、愛をさけぶ』が若者から圧倒的な支持を得、文芸書としては異例のロングセラーとなっている片山恭一さん。近著『空のレンズ』ではデジタル世代を描き、また異なる作風を披露、さらに今後はご自身と同世代の人々の物語を書く予定だとか。そんな片山さん、理系出身で、意外にも高校生までは文芸書とは縁がなかったそう。では、読書に目覚めたきっかけとは…?
(プロフィール)
1959年愛媛県生まれ。福岡県在住。九州大学卒業後、1986年「気配」で『文學界』新人賞を受賞しデビュー。
主な作品に『きみの知らないところで世界は動く』(新潮社刊)、『ジョン・レノンを信じるな』(角川書店刊)、『世界の中心で、愛をさけぶ』(小学館刊)、『満月の夜、モビイ・ディックが』(小学館刊)、最新作として『空のレンズ』(ポプラ社)がある。
【本のお話、はじまりはじまり】
――片山さんの幼い頃の読書歴を教えてください。

片山 : 大学までほとんど文芸書を読んだことがなかったんです。学部は農学部ですが、教養課程で国文学の授業があって。レポートを書くために夏目漱石の主な作品を読んだのが、文学に触れたきっかけです。それと実家の裏に高校の世界史の先生が住んでいて、夏休みに帰省して遊びにいくと、「こういうのも読んでみんね」と紹介してくれたのが、野間宏、堀田善衛、埴谷雄高といった戦後派でした。
――…いきなり、かなりカタイところから入りましたね。
片山 : 理系の人間だった僕にとっては、カルチャーショックみたいなものでした。漱石ですら新鮮でしたから。知識欲が旺盛だったので、目ぼしいものは全部読もうと、文学全集的な基準で明治以降の近代文学をひと通り読みました。
【読書の原点】
――ご自身も小説を書こうと思ったきっかけとなった作家・作品はあるのですか?
片山 : 大江健三郎を読んだときに、はじめて親近感を持ったんです。それまで、野間宏でも大岡昇平でも、戦争体験というものが大きくて、小説はそうした特別な体験がなければ書けないものだと思っていました。でも初期の大江さんの作品は、例えば「奇妙な仕事」が大学生のアルバイトの話であるように、日常生活を題材にしています。これなら自分にも書けるんじゃないかと…そう簡単なものじゃないですけどね(笑)。
――大江氏の作品のなかで一番好きなのは?

- 『芽むしり仔撃ち』
- 大江健三郎 編纂
- 新潮文庫
- 420円(税込)
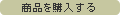
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
片山 : 初期の作品はほとんど好きですが、強いてあげれば『芽むしり仔撃ち』かな。あの人の性に対する独特の感受性が鮮やかに出ていると思います。四国の山の中が描かれているのですが、僕も四国出身なので、地理的にも親近感があります。
――その後も、読書傾向としては、近代文学を中心に…?
片山 : 大学に入った当初は、植物学か生物学を専攻したいと思っていました。それが文学に触れて興味の対象が移ったため、農業経済学を専攻すれば人文系の本が読めるだろうと、途中で軌道修正しました。論文を書かねばならないこともあって、スミス、リカード、マルクスといったところを読み始めました。僕、卒論はマルクスで、修論はエンゲルスなんですよ。
――ずいぶん傾向が変わりましたね。
片山 : マルクスも、初期はヘーゲルの影響があって哲学的なんです。そんなこともあり、ヨーロッパの近代哲学をひと通り勉強しようと、デカルトやライプニッツあたりから構造主義まで、自分なりに読みました。
――その傍ら、小説も書き始めていたのですか。

片山 : 僕は大学院の博士課程まで進みましたが、アカデミズムの中でなにか書くとすれば論文ということになります。でも論文は自分を表現するものではなく、仕事で書くものだから、いくら書いても不全感というか、欲求不満が残るんです。それを解消するために小説を書きはじめました。22、3歳の頃ですね。でも、文学サークルに入るわけでもなく、小説を書いていることを友達に話すわけでもなかった。なんとなく気恥ずかしくて。でも自分の書いているものがどういうレベルにあるのか知りたくて、いくつかの新人賞に応募しました。たまたま『文学界』から最終選考に残ったという葉書がきまして。その時は嬉しかったですね。じゃあ、もう少し頑張ってみるか、と。
――ご自身で書く時、文体など参考にされたのは、やはり大江健三郎氏なのですか?
片山 : いいえ、大江さんの文体は自分のスタイルではないと感じました。というか、一人称の「ぼく」を使って書くと、自分と作品との距離が近すぎて、小説を書いているという感じがしなかったんです。それで古井由吉さんに入れ込みまして。文体から言葉づかいまで、臆面もなく真似していましたね。『文学界』の新人賞をもらった時も、選評に「古井さんの文章に似ている」というのがあって、「そりゃあ似ているはずだよ、真似してるんだから」と思いましたけどね。古井さんの作品の中でとくに好きなのは『栖(すみか)』や『親』、『槿(あさがお)』など。エロスはエロスなんだけれど、性愛というより観念的・形而上的。そこに惹かれて、一時のめりこんで読んでいました。
――ただ、最近の作品は、そうした文体から離れていますよね。

片山 : 古井さんは今でも好きで読んでいるんですが、書くとなると、古井さんには及ばないし、古井さんは2人も要らないだろうと。それで今度は、意識的に古井さんから離れようとしました。その時にずいぶん影響を受けたのがアメリカ文学です。ヘミングウェイの『日はまた昇る』とか。主人公のジェイクも好きですし、パリのアメリカ人がピレネー山脈を越えてスペインまで闘牛を見に行くというロケーションにも惹かれました。僕が読んだのは、新潮文庫から出ていた大久保康雄さんの訳で、乾いた感じの文章を意識的に真似しようとしました…どうも真似ばかりしていますが(笑)。
――本を選ぶ際に基準にしていることは?
片山 : 系統的に読むことが多いですね。書評など、どこかから情報が入ってきて、1冊読んで面白ければ、その作家に関連したものをつづけて読みます。ただ、ずっと小説を書いてきているので、本を選ぶ時でも、作品を書く際のヒントになりそうなものがないかな、という目で探すようになっています。
――気になる書評家、批評家は。
片山 : 昨年亡くなられた日野啓三さんが新聞などで取り上げる本は、たいてい読んでいましたね。自分と日野さんは似たところがあるのかなという気がします。日野さんには「人間はどこからきて、どこへ行くのだろう」という、一貫したモチーフがある。日本の作家は私小説の影響か、日常生活や男女のことを書いて終わり、ということが多く、あまり"人間はどうなるのか""このままで世界はいいのか"という視点はない。日野さんは長いスパンでものを考える方で、人類の発生や宇宙のことをよく話されていました。そういうところも、僕にはしっくりくるんです。
【最近買った本】

- 『岬』
- チャールズ・ダンブロジオ(著)
- 早川書房
- 2,415円(税込)
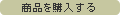
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com

- 『海辺の家』
- メイ・サートン(著)
- みすず書房
- 3,150円(税込)
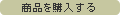
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
――最近読んだ本のなかで面白かったものは。
片山 : 何年か前に、チャールズ・ダンブロジオの『岬』という短編集を読んで、非常に感心しました。シアトルに住んでいる人らしいのですが、同世代の作家として、僕もこれくらいのものが書きたいなと思いました。なんというか、ひとつひとつの物語が破綻なくできているんですね。小説の多くは、登場人物を他から任意に持ってきても成立したり、たまたま思いついた会話を並べているという印象を与えるものだったりと、内部構造にどこか弱点をかかえているものだけれど、この本に収められた作品は、その物語の中にいるべき人が、語るべきことを語っている。「やるなあ」と思いました。
――本を読む時間帯など、読書スタイルは?
片山 : 小説を書くのは朝の8時から12時まで、家族がみんな出払っている時です。その間にウォーミングアップとして読んだり、インスピレーションを得るためと称して、いろんな本をぱらぱらめくったりしています。実は仕事に取りかかりたくないがための現実逃避だったりして(笑)。だから純粋に読書を楽しんでいるという感じではないんです。最近読んでいるのは、アメリカの女流詩人メイ・サートンの日記。『海辺の家』や『独り居の日記』など、晩年のものです。庭仕事や読書のことを、自身の老いや孤独とからめて淡々と書いているのですが、これがいいんです。強靭な内省力に貫かれてましてね。彼女は当時六十歳を過ぎていたはずですが、人生と全然折り合いをつけてないんですね。たいしたものだと思います。
――片山さんご自身は、日記はつけているのですか?
片山 : メモ程度のものはつけています。その日の天気と、何時に起床して、何を読んだかくらいですが。大学に入ったときに、とにかく1年に100冊は本を読もうと決めて、それをチェックするためにつけはじめ、今までずっとそのノルマはクリアしてきています。学生時代のノートを見るのは恥ずかしいですね。非常に生意気なことを書いていて、なんてイヤな学生だったんだろう(笑)。
――そうして蓄積されたきた読書歴が、片山さんの作品世界にも影響しているんですね。
片山 : そうですね。ただ、新人賞をもらったときに編集者から、「あなたの今後の課題はペダンチックなところをいかに消すかということです」と言われたのが、妙に応えてまして。哲学的な思索が、小説としての感興を削いでいるというんです。だから現在も、理屈っぽいところはあまり出さないようにしています。『世界の中心で、愛をさけぶ』でもエマニュエル・レヴィナスやシモーヌ・ヴェイユを使いましたが、直接的ではなく、たとえば祖父の台詞に紛れ込ませるとか、それなりに工夫はしているんです。

- 『きみの知らないところで世界は動く』
- 片山恭一(著)
- ポプラ社
- 1,575円(税込)
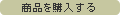
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com

- 『世界の中心で、愛をさけぶ』
- 片山恭一(著)
- 小学館
- 1,470円(税込)
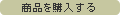
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com

- 『空のレンズ』
- 片山恭一(著)
- ポプラ社
- 1,470円(税込)
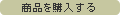
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com

- 『もしも私が、そこにいるならば』
- 片山恭一(著)
- 小学館
- 1,365円(税込)
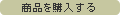
- >> Amazon.co.jp
- >> HonyaClub.com
――今後の刊行予定を教えてください。
片山 : 処女作『きみの知らないところで世界は動く』が絶版になっているので、夏頃にポプラ社から復刊したいと思っています。そして秋には小学館から『もしも私が、そこにいるならば』という中篇集を出す予定です。『世界の中心で、愛をさけぶ』『満月の夜、モビイ・ディックが』とつづいてきた、あいだに読点の入る長いタイトルシリーズは、これでひとまず打ち止めということになります。
――『もしも私が〜』も、これまでのように、10代の少年少女の姿が描かれているのでしょうか。
片山 : この作品集では20代、30代の大人が主人公です。これまではナイーブなもの、ピュアなものを書きたいという気持ちもあって、若い人たちを主人公に書いてきましたが、そこには僕に就職経験がなく、実社会を舞台にしたものが書きにくいという事情もあったんです。今後は少し登場人物の年齢を上げて、普通の大人というか、社会生活を営んでいる人物を主人公に書いていくつもりです。今年刊行した『空のレンズ』も、これまでとは別の傾向の小説ですが、そんなふうに登場人物の年齢や物語の切り口を変えて、作品の世界を広げていきたいですね。ただ、中心にあるのは、やっぱり恋愛だと思うんです。人を好きになるということが、人間のアルファでありオメガであると思っていますから。
(2003年5月更新)
取材・文:瀧井朝世
WEB本の雑誌>【本のはなし】作家の読書道>第20回:片山 恭一さん